日本酒物語

第七話:十石桶が出現
室町中期から末期にかけて「南都諸白」を生んだ奈良・正暦寺(しょうりゃくじ)の酒造技術は、日本酒の酒造史上画期的なものでしたが、この頃、酒造りをさらに盛んにする仕込み用の大桶(十石桶)が出来たことも見逃せません。
これまでの酒造りは、壷や甕(かめ)だったので、大きくても1石か2石しか造れませんでした。従って大量に造る酒屋では甕を100個以上も並べて造っているところが少なくなかったそうです。
この頃、甕のかわりに桶も造られるようになりましたが、桶造りの技術が未熟で酒が漏れるので、水に漬けると膨張する柳の木で造ったと言われています。(祝用の「柳樽」の語源の一説) それが室町中期になると、中国から板の平面を湾曲して削れる鉋(かんな)(正直鉋=しょうじきがんな)が輸入され、桶職人がこれを使い出したので、一度に大量に仕込める大桶が出来るようになり、量産化の発端になりました。
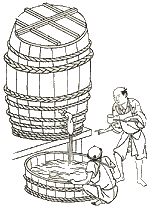
「伊丹(いたみ)諸白」の台頭
その頃から、わが国の酒造地図は少しずつ変わりつつありました。南都の専売だった諸白が、地方のあちこちで「○○諸白」として売られるようになり、なかでも摂津国の伊丹、池田の諸白が台頭してきて、京、大坂はもちろん、やがて江戸表でも人気の的になりました。(大坂が大阪になったのは明治になってからです)
伊丹は、江戸前期から五摂家筆頭近衛家の領地になり、近衛家の庇護(ひご)のもとに造り酒屋が栄え、「伊丹諸白」は将軍家の御膳酒となりました。そしてその名声は「丹醸(たんじょう)」(伊丹で醸された酒)ともてはやされ、元禄15年(1702)には5万石も造っていたそうです。当時としては大変な量でした。
年に5回の酒造り
当時の酒造りは、新酒、間酒、寒前酒、寒酒、春酒と一年に、5回造っていました。秋の彼岸頃から造り始める「新酒」。新酒と寒前酒の間に造る「間酒」。そして文字通り寒に入る前に造る「寒前酒」。寒中に造る「寒酒」。さらに春になって造る「春酒」です。しかし、味の点では、やはり、「寒酒」が一番いいとされていました。
伊丹に移ってから、酒造りの方法はさらに進歩しました。「南都諸泊」の三段仕込みは3回同量ずつ原料を加えていましたが、伊丹では、仲添は初添の二倍、留添は仲添の二倍と量を増やしていきました。これは現代の仕込み方とほぼ同じです。
ただ、仕込水の量が減っているので、とろりとした、甘い、油のような酒だったと言われています。

